「こころ」の強さ(その2)
visibility967 edit2023.12.30

茂木健一郎さん(脳科学者)は、次のように言っております。(私の主観も入った言葉です)
やさしさは教養から生まれる
そもそも、『やさしさ』とは何なのでしょうか。
要するに「他人の気持ちを分かった上で、寄り添うことが出来る・求められる」だと思います。
ではどうすれば、相手の気持ちを的確に分かってあげれる(推理する)ことができるのでしょうか。
その一つは経験でしょう。
「相手の気持ちが分からなかった経験」
「自分の気持ちを分かってもらえなかった経験」
そういう積み重ねが、『推理力を高める』ことになるのです。
言ってしまえば、『他人の気持ちを理解するためには、広い意味での教養が必要になる』ということです。
『やさしさ』とは、「相手の気持ちを思いやる」ところから始まるのだと思います。「相手の気持ちを推察」したり、「こういうことをしたら(言ったら)相手はどういう気持ちになるだろうかと推測」したりする。
その為には、『経験』が役立つわけです。
ただ、人の気持ちを推理するのは難しいことです。ましてや自分が経験していないこととなれば、なおさらです。
そういう意味では、「つらい経験」「悲しい経験」がある人は、『人のつらさや悲しさを理解しやすい』でしょう。
たとえ相手の気持ちが明確には分からなくても、「相手を思いやる気持ち」が大事なのだと知っているからです。
その気持ちが、自ずと『態度として表れ』相手に伝わればいいのではないでしょうか。
「人の気持ち」を分かるために、また「自分の経験」を確かなものにするためにも、まずは『自分の気持ちを知る』ことが大事だと思います。
「自分はこういう時にこういう気持ちになった」
などを知っていれば、人の気持ちを推察する際に役立つでしょう。
そして『自分を育てる』ためにも、
「自省する時間をもつようにする」
「生活の中での自分の感情・気分を振り返ってみる」
すると、いいのではないでしょうか。
その他にも、「小説を読む」とか、「映画やドラマを観る」、「心(心理)に関する本やブログを読む」など、人の気持ちを理解するヒントを得られることはいろいろあるでしょう。
『広い意味での教養』
を獲ることが、人の気持ちを思いやり、やさしくする行為につながるのです。
あとは、「人にやさしくすることを実践し、その経験を活かしながら続けていく」ことで、「やさしさ」「人間性を高める」ということが出来る様になるのだと思います。
------------------------------
さて、ここでいう『教養』とは、「学問」ではなく「心理」の教養が必要であると書かれています。
精神疾患を持つ人にとって、『相手の気持(つらい・悲しい)を理解する』ことは、容易だと思います。でも、いざ自分自身がそうなった時、その経験を生かすことが出来ないのです。
それはなぜでしょう・・・。
そう、ここでも「心の強さ」というキーワードが重要となってくるのです。
では、本当の「心の強さ」とは、いったいなんなのでしょうか?
ますます理解するのが難しくなってきました・・・
- ココトモ「交換日記」を書いて繋がろう♪
-
今日の出来事、気持ち、頑張ったことをみんなでシェアする『交換日記』ができました。 自分の日記を書いたり、他の人の日記にコメント&フォローしたりすることで交流を深めることができます♪
交換日記はこちら



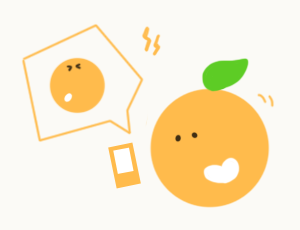
コメントを投稿する