「性別違和」を知ろう 第2話
visibility2,755 edit2025.05.07
皆様お久しぶりです。李夜と申します。
第2話目となる今回は、なんか言葉がややこしい性的マイノリティの世界を話したいと思います。
トランスジェンダーと性別違和
前回トランスジェンダーを「体の性と心の性が一致しない人」と表現しましたが、今回はもう少し焦点を当てていきたいと思います。
トランスジェンダーには、おおきく分類して4種類が該当します。
- 体は男性、心は女性。
- 体は女性、心は男性。
- 体は任意、心が中性。
- 体は任意、心が両性。
よく混同されるものに「性別不合」「性別違和」「性同一性障害」などがあると思います。「性別不合」は同じ意味なので混同しちゃって大丈夫なのですが、後の2つは少し違います。
性同一性障害
これまでは、体の性と心の性が異なる人を「性同一性障害」として、精神疾患と診断されていました。しかし、2022年に”性の健康と状態に関する状態”という分類に変更されています。
その背景として、性自認への社会全体の理解が進んだことがあります。
男性は外で働き、女性は中で働く。
昔はさんざん言われていましたね。凝り固まった”性別ごとの役割”のステレオタイプが思考を阻害していました。
今はどうですか?
女性も会社で働き、男性が育休を取る。研究職に従事する女性も居れば、看護師として働く男性もいます。
彼らは男性らしく、または女性らしくないのか。そんなこと決められるわけがないですよね。
そもそもの話、「男性らしさ」「女性らしさ」って、はっきり分けられるものでしょうか?
性自認というのは、白か黒かの二択ではありません。
それはまるで色のようなものです。
赤と青、はっきりした色もあれば、その間に紫や桃色、藍色や群青といった無数のグラデーションがありますよね。
性自認も同じように、人によって濃淡があり、混ざり合い、時には変化していくことさえある。
そして、それらはどれも「おかしい」わけでも、「間違っている」わけでもありません。
私たちは誰もが、女性的な面と男性的な面の両方を持ち合わせています。
たとえば、感情に敏感で人に寄り添える男性。
合理的に考え、的確に判断する女性。
それって本当に、「らしくない」ことでしょうか?
トランスジェンダーである彼等だって同じなのです。確かに該当する人物は少数で「普通」とは違うかもしれない。でもそれは「おかしい」わけではないのです。
彼らは病気ではない。
それは一人一人の個性であり、状態であり、尊重されるべき個人なのです。
色々脱線しましたが、こうして現在では「性同一性障害」という言葉は使われなくなりました。
もしこの言葉を使わなければならないとき、「性別違和」という言葉を使ってあげてください。私のコラムでも、今後登場することはないでしょう。
性別違和
さて。
上では性同一性障害改め性別不合の説明となりましたが、次の話題は性別違和となります。
性別不合は状態を表し、性別違和はその状態によって生じる心理的苦痛を指します。
例えば声、名前、体格や行動心理に始まり、周囲の環境、自分への接し方。その人によって感じる苦痛は様々です。
共通するのは周りと自分の違いに心がすり減る事。
心は女性なのに、電話口で「低い声の男性」として扱われる。
心は男性なのに、書類上の名前で「さん」ではなく「ちゃん」と呼ばれる。
制服や更衣室、トイレ、住民票や履歴書――日常のあらゆる場面で、「他人が決めた性別に合うふり」を求められる。
小さな違和感の積み重ねが、やがては「自分の存在が否定されている」ように感じてしまう。
それが、性別違和です。
「そんなの気にしすぎだ」と言われることもあります。
けれど、それは「靴が合わなくて痛い」と訴える人に、「我慢すればいい」と言っているのと同じこと。
痛みを感じているのはその人自身であり、他人が決めることではありません。
私たちは「普通」になろうと無理をしているのではありません。
ただ、「自分らしく生きたい」と願っているだけなのです。
第2話目のコラムはこれにて終わりとします。最後まで読んでいただき、まことにありがとうございました。
次は第3話でお会いしましょう。(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)ペコリ♡…*゜
- ココトモメンバーたちと交流しよう♪
-
ココトモメンバーたちと交流するための『メンバーのお部屋』掲示板ができました。気になるメンバーと気軽にお話することができます。ぜひ色んなメンバーのお部屋に遊びに行ってみてください♪
メンバーのお部屋はこちら



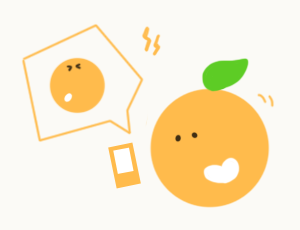
コメントを投稿する