親はみな「毒親」??
visibility1,349 edit2023.03.05

毒親という言葉のインパクトの強さに、私はまだちょっと慣れないでいる。
この言葉が持つ怨念の強さみたいなものにいまだに戸惑ってしまう。
というのは、子どもはいないけれども私自身が親世代になったからかもしれない。
毒親に苦しむ子どもに「辛いよね」「苦しいよね」と寄り添うより先に、
必死に子育てしているだろうにそんなことを言われて「かわいそう」と、親の方に同情してしまう。
いつの間にか子どもの気持ちより親の気持ちに感情移入しやすくなってしまったようだ。
という私の感想などどうでもよくて、今や「毒親」は多くの人に浸透しているようだ。
これは幅広い世代の人が親との関係に悩んでいることの表れだろう。
このインパクトの強い言葉は、親に対するイライラやモヤモヤを見事に言い表した言葉だ。親子関係に悩む人にとって言いえて妙、わが意を得たりといったところだろう。
ところで私は、この言葉自体に強い毒があり、中毒性があるような気がしている。
どこか安易に使われているような気がしているのだ。
確かに、世の中には虐待で子どもを殺すような毒とも凶器とも言える親もいる。
そこまでいかなくても言葉や態度で子どもを苦しめ痛めつける親もいる。
それにしてもあまりにも頻繁に「毒親」という言葉が見かけられる。
それも当然のことだ。
誰でも親子関係には悩むものだ。
どんなに人間関係を断ち切って孤独になろうとしたところで、一番最後まで残るのが親子関係だからだ。
では、毒である親と毒ではない親の差とはなんなのだろうか。
家族が健全に機能している状態、お互いが分かりあえている状態なら毒がないといえそうだ。
お互いに傷つけ合うこともなく、意見がぶつかっても冷静に話し合いができる。
その逆、お互いに分かり合えない関係はどうだろうか。
相手を理解せず、受け入れず、傷つける。
これは毒といえそうだ。
そうだとしたら、親とは、程度の差こそあれ多少は毒になるものではないだろうか。
たいていの人は生まれて初めて接する他者が親だ。
子どものうちは親子ともにお互い混同しやすいが、親と子は別の人間だ。
いくら教育を受け、影響を受けてきたとはいえ子どもは親から独立した別個の人格だ。
全ての考えや思いが合致するわけがないのだ。
そして、人間は相手を思い通りにしてやろうというときにぶつかる。
親子がぶつかったときにお互いに腹を立てるのは自然なことだ。
なんで分かってくれない。なんで思い通りにさせてくれない。
そのとき、親は子にとって「毒」になる。
それと同時にまた、子も親にとって「毒」になっているのではないだろうか。
お互いがお互いの「毒」になっていては共倒れしてしまう。
どうしたら「解毒」できるのだろうか。
このとき大事になるのが日ごろからのコミュニケーションだ。
ぶつかっても大きな亀裂を生まないために、日ごろから子どもの話を聞く体勢を親側が整えておく必要がある。
「いつでも聞くよ」「何を言っても大丈夫だよ」という安心と信頼を与えることが大事だ。
といってもそんなに大仰なことはしなくていいと思う。
「おはよう」「おやすみ」「行ってきます」「行ってらっしゃい」といった挨拶ができていれば、一番低いハードルはクリアしていると思う。
(なぜ親側だけにコミュニケーションの責任を負わせるかといえば、たいていの子どもは親の話など聞けないものだからだ。)
と、偉そうに書いたが「解毒」方法については私もまだまだ勉強中なのでよく分からない。
私が言いたいのは、必死に子育てをしている親御さんたちに「毒親」という衝撃的な言葉に怯まないでほしいということだ。
大体の親は子どもにとって「毒親」になりうる。
そして、どんな人間関係にも毒はつきものだ。
毒親、毒子、毒友、毒上司、毒部下、毒彼、毒彼女…。
大事なのは毒を毒のままにせずに解毒しようという努力だと思う。
そのためには日々のコミュニケーションがとても大事になる。
これが解毒されずに溜まりに溜まったとき、本物の「毒」になってしまうのではないだろうか。
- ココトモYouTubeはじめました♪
-
このたび、ココトモの取り組みや想いを発信するYouTubeチャンネルをはじめました。ぜひ応援&チャンネル登録いただけると嬉しいです(*´`)
YouTubeはこちら



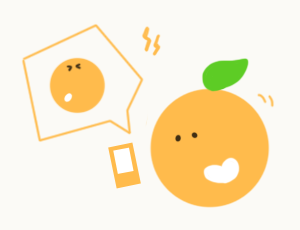
コメントを投稿する